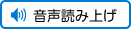令和6年(ネ)第259号 損害賠償請求控訴事件(原審・松山地方裁判所宇和島支部令和4年(ワ)第47号)について
2025年04月08日更新
事件番号等:原審
- 事件番号 令和4年(ワ)第47号
- 事件名 損害賠償請求事件
- 裁判所 松山地方裁判所宇和島支部
- 原告 1名
- 被告 愛南町
事件の内容
原告が、被告に対して、文書の取扱いをめぐる紛争において、
①被告がある文書を違法に廃棄し、また廃棄したことを原告に伝えなかったこと、
②被告が①と別の文書について原告が公文書開示請求をしていたにもかかわらず、従前訴訟の控訴審まで不開示決定を行わなかったことにより、
それぞれ原告が憲法12条によって保障されている憲法保持活動を妨害されたと主張して、慰謝料20万円の支払いを求め令和4年12月23日に松山地方裁判所宇和島支部に提起した国家賠償請求訴訟です。
令和6年9月6日 判決言渡 松山地方裁判所宇和島支部
(主文)
1.被告は、原告に対し、5万円を支払え。
2.原告のその余の請求を棄却する。
3.訴訟費用は、これを4分し、その3を原告の負担とし、その余を被告の負担とする。
(裁判所判断 抜粋)
争点1 「A議員の発言に対する要望書」(以下「本件要望書」という。)の廃棄等に関する違法性について
(1)C議長が本件要望書を廃棄したことについて
被告における公文書の定義は、原則として「実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているもの」をいう。
本件要望書は、C議長がB副町長から同文書を受領後、その内容や形式から私信であると判断して愛南町議会事務局等に交付することなくC議長が個人的に保管しており、最終的にはC議長自身が廃棄している。こうしたC議長のみが本件要望書を保管しており、愛南町議会事務局が何ら関与していなかった状況を踏まえると、本件要望書は「当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているもの」には該当しないから、本件要望書が廃棄された令和元年12月末時点でも、本件要望書が公文書であるとは言えず、これを前提とする原告の請求には理由がない。
(高裁補正抜粋下線)仮にC議長から議会事務局に引き継がれ規程に則った処理が行われるべきであったと解する余地があり、そのような取扱いを受けていれば廃棄されることもなく開示対象となった可能性もある。しかし、公務員による公権力の行使に国家賠償法第1条1項にいう違法があるというためには公務員が、当該行為によって損害を被ったと主張する者に対して負う職務上の法的義務に違反したと認められることが必要であるところ、被控訴人の保有する文書の公開を請求する権利を認めるものであるから、情報公開請求がされる以前の段階で、請求者の具体的な権利・義務に関わりのない公文書一般の保存・管理に関し、法的義務を認めるべき根拠になるとは解されない。C議長が本件要望書を廃棄した時点では、控訴人は本件要望書等について特段の利害関係を有しておらず、また控訴人による同文書の開示請求もなされていなかったことからするとC議長が本件要望書を廃棄して議会事務局に引き継がなかったことにつき、控訴人に対する関係で、国家賠償法第1条1項の違法があるということはできない。
以上によれば、C議長が本件要望書を廃棄した点に関する原告の主張は採用できない。
(2)被告が本件要望書を廃棄した事実を原告に伝えなかったことについて
愛南町情報公開条例では、文書の不開示決定に際して(高裁補正下線)、文書不存在という理由に加えて原告が主張するような具体的な理由を説明することを求めておらず、その他原告が主張するような事由を被告が原告に対して説明すべき義務があったことを基礎づけるような事情もうかがわれない。
以上によれば、被告が本件要望書の不開示に際して、C議長による同文書の廃棄を説明すべき義務があったとの原告の主張は採用できない。
争点2 本件要望書の廃棄等に関する原告の損害について
よって、本件要望書の廃棄に関する原告の主張はいずれも採用できないから、判断するまでもなく、上記原告の各主張を前提とする原告の請求には理由がない。
争点3 申合せ資料開示手続に関する違法性について
愛南町議会は、原告から令和2年3月26日に申合せ資料を含めた議員協議会記録等の公文書開示請求を受けていたところ、同年4月7日、原告に対し、申合せ資料を開示対象外とする旨の記載がない公文書開示決定通知書を送付している。しかし、D議会事務局長は、同月9日、原告に対し、申合せ資料は公文書ではない旨の口頭説明を行ったのみで書面による不開示決定を行わなかった。愛南町議会は、公文書開示不作為違法確認請求事件訴訟の訴訟提起や控訴審への控訴提起後である令和3年11月18日に、原告に対し、申合せ資料の開示決定通知書を送付している。
被告においては、原則として公文書開示請求があった日から起算して15日以内に開示決定又は不開示決定を行わなければならず、事務処理上の困難その他正当な理由がある場合には15日以内の延長を行うことができ、また開示請求にかかる公文書が著しく大量であり、開示請求があった日から30日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、開示請求にかかる公文書のうち相当の部分について条例が規定する期間中に開示決定をし、残りの公文書については相当の期間内に開示決定等をすれば足りるが、本件では、原告が申合せ資料を含めた公文書開示請求を行った令和2年3月26日から、申合せ資料の正式な開示決定通知が原告に到達した令和3年11月19日まで、603日間を要している。また、原告による申合せ資料を含めた公文書開示請求に対して、延長等の手続きが取られたような事情はうかがわれない。
また、愛南町議会は令和2年4月7日頃、公文書開示請求に対する公文書開示決定通知書を送付し、その後D議会事務局長が、令和2年4月9日の時点で、口頭で申合せ資料を不開示とする旨を原告に述べたものの、同月28日にはC議長が申合せ資料を事実上原告にデータで送信している。これらの状況からすれば、愛南町議会において、申合せ資料を含めて原告が行った公文書開示請求に対して開示又は不開示の決定を行うことは容易であったと言わざるを得ない。
そうすると、遅くとも令和2年4月28日の時点で、C議長が原告に申合せ資料をデータで送付している以上、この時点で愛南町議会が開示又は不開示決定を行うことは何ら妨げるものはなかったものであり、この時点で開示又は不開示決定を行うべき職務上通常尽くすべき注意義務があったといえる。にもかかわらず、愛南町議会は漫然とこれを怠り、令和3年11月19日の開示決定通知書が原告に到達するまで開示又は不開示決定を行わなかった。原告が行った公文書開示請求が令和2年3月26日であることからすれば、その遅延は社会通念上一般人において受忍すべき限度を超えたものと言わざるを得ない。
そのため、愛南町議会は、申合せ資料についての開示決定又は不開示決定を行うべき職務上の注意義務があったのに、これを怠り、不作為の違法状態を作出したといえるから、被告は国家賠償法1条1項の責任を負う。
原告は、不作為により、憲法12条に基づく原告による申合せ資料の公文書開示請求や本件訴訟等の憲法保持活動が妨害されたと主張して、この権利侵害に対する違法性を主張しているが、憲法12条は、国民の自由及び権利について、「国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。」と規定するのみで、具体的な努力の内容や保持されている状況を規定しているものではないから、憲法12条から直接原告の具体的な法的権利を認めることはできない。
しかし、原告は、令和2年4月に公文書開示決定がなされたにもかかわらず、申合せ資料に関して、令和3年11月19日まで書面による開示又は不開示決定を受けることができなかった。
申合せ資料は、あくまで被告の議会に属する議員間の申し合わせ事項であり、その内容も原告を含めた住民に直接影響する内容ではないが、公文書開示は住民が地方公共団体である被告の活動内容等を確認、検討するうえで重要な手掛かりとなる手続であること、愛南町情報公開条例でも、「この条例は、愛南町の保有する公文書の公開を請求する権利を明らかにする」と規定されていることに鑑みれば、原告には、申合せ資料の公文書開示請求に対して、同条例に基づいて適切に開示を受けることができる権利が具体的に存在していたといえるから、不作為はこの原告の権利を侵害したものと評価できる。
以上によれば、被告の不作為は国家賠償法上違法というべきであるから、被告は損害賠償義務を負う。
争点4 申合せ資料開示手続に関する原告の損害について
原告は、令和2年4月に公文書開示決定がなされたにもかかわらず、申合せ資料に関して、令和3年11月19日まで書面による開示又は不開示決定を受けることができなかった。申合せ資料の内容自体は原告に直接影響するものではないが、原告の公益的観点からの開示請求である点も上記のとおり原告の具体的な権利を侵害したものとして、慰謝料算定の上で考慮すべきである。
そのうえで、原告には、申合せ資料の開示のために公文書開示不作為違法確認請求事件訴訟及び控訴審において訴訟活動を行うといった負担が生じていること、一方で、申合せ資料の内容そのものは令和2年4月28日の時点で原告も把握することができていたことを併せて考慮すると、原告の精神的苦痛を慰謝するに足りる金額としては、5万円をもって相当とする。
(結論)
被告は、原告に対して、申合せ資料の開示に関して5万円を賠償すべきであるから、その限度で原告の請求は理由があるから認容し、その余は理由がないから棄却することとし、主文のとおり判決する。
一審判決後の経過
令和6年9月10日 議会は、議員全員協議会を開催し、判決を受け議会として控訴するべきか否かの各議員の意思は、議長を除く出席議員13名の多数決により確認し、3名が控訴することに賛成である結果を町執行部に報告しました。
令和6年9月13日 町は、議会の意向を参考に控訴しないと判断、松山地方裁判所宇和島支部判決を受入れました。
令和6年9月20日 原告は、松山地方裁判所宇和島支部判決に一部不服があるとして高松高等裁判所に控訴しました。
事件番号等:控訴審
- 事件番号 令和6年(ネ)第259号
- 事件名 損害賠償請求控訴事件
- 裁判所 高松高等裁判所
- 控訴人 1名
- 被控訴人 愛南町
令和7年3月6日 判決言渡 高松高等裁判所
(主文)
1.本件控訴を棄却する。
2.控訴費用は控訴人の負担とする。
(裁判所判断 抜粋)
1.補正するほかは、原判決のとおり
2.控訴人の補充主張に対する判断
控訴人は、公文書としての保管義務が生じていたと主張するが、本件要望書が公文書に該当しないことは、原判決のとおり。また、控訴人は、公文書要件を欠くに至った責任が情報公開条例実施機関にある以上、業務妨害の不法行為責任を追及することができるとも主張するが、廃棄について、控訴人に対する関係で、国家賠償法上1条1項の違法があるといえないことは、原判決を補正の上引用したとおりである。
(結論)
控訴人の請求は理由がないから棄却すべきであり、これと同旨の原判決は相当であって、本件控訴は理由がないから棄却することとして、主文のとおり判決する。
二審判決後の経過
令和7年3月22日上告なく判決確定
令和7年4月7日賠償金5万円を支払いました。
愛南町城辺甲2420番地
電話番号:0895-72-7320
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください